『ミッドサマー』以上に難解——そう言われるのも納得の、アリ・アスター監督最新作。上映時間の長さ以上に、観る側の思考を休ませてくれない作品でした。
事前情報は「アリ・アスター監督作品」という一点のみ。結果的に、その“まっさら”な状態で観られたこと自体が、本作の体験価値を最大化してくれた気がします。
※以下はネタバレを全面的に含みます。
本作を未鑑賞の方はご注意ください。
はじめに|「理解できない」こと自体が正解の映画
『ボーはおそれている』は、アリ・アスター監督のフィルモグラフィーの中でも、群を抜いて理解を拒む作品です。
ホラー映画としての恐怖、スリラーとしての緊張感、コメディのような誇張表現、神話的・象徴的イメージが混在し、観客は終始「これは何を見せられているのか?」という感覚に晒され続けます。
しかし本作は、
「理解しようとして混乱する体験」そのものを観客に強いる映画
だと考えると、極めて一貫した構造を持っています。
なぜならこの映画は、
重度の不安障害・愛着障害・精神病理を抱えた当事者の主観世界
を、可能な限り忠実に再現しようとした作品だからです。
作品の前提|これは「現実」を描いた映画ではない
まず最初に押さえておきたいのは、
この映画は「現実世界で起きた出来事」を描いていない、という点です。
物語の大部分は、
- 妄想
- 幻覚
- 記憶の歪み
- トラウマによる象徴化
これらが一切区別されないまま提示されます。
観客が混乱するのは当然で、
それこそがボーが日常的に生きている世界なのです。
あらすじ再整理|「帰省」という名の精神的旅路
ボーは、極度に不安が強く、母親の言動に支配されて生きてきた中年男性です。
物語のきっかけは、母からの電話と、その直後に伝えられる「母の死」。
帰省しようとした瞬間から、ボーの世界は完全に崩壊します。
- アパートの外は無法地帯
- 部屋は侵入され放題
- 助けを求めても、誰も助けてくれない
この「帰省できない状態」は、
単なるトラブルではなく、心理的に母から離れられない状態の象徴です。
統合失調症的世界観の再現
本作はしばしば
「ボーは統合失調症なのか?」
と議論されます。
医学的診断として断定することはできませんが、
描写としては以下の特徴が顕著です。
現実検討能力の破綻
- 異常な出来事を異常と判断できない
- 他者の悪意を過剰に確信する
被害妄想
- 常に「自分は責められている」「罰を受ける存在だ」という確信
- 最終盤の“裁判”は、典型的な自己糾弾型妄想
幻覚・幻聴的表現
- 街の異常な暴力性
- 隣人の騒音訴え
- 突然現れる脅威的存在
重要なのは、
映画はそれを「病気だ」と説明しないことです。
説明しないことで、
観客は「わからなさ」をそのまま体験させられます。
愛着障害という視点|すべては母から始まっている
この作品を貫く最大のテーマは、
母子関係の歪みです。
ボーの母は、
- 過干渉
- 支配的
- 罪悪感を植え付ける
- 愛情と罰を混同する
という、不安型+支配型愛着の典型です。
母のメッセージの特徴
- 「あなたのため」と言いながら恐怖を与える
- 息子の自立を裏切りと捉える
- 母の感情=世界の正解
ボーにとって母は、
- 守ってくれる存在
- 罰を与える存在
その両方であり、
安全基地になり得なかった母です。

「出生」がトラウマになるという発想
本作の冒頭が羊水から始まることは、非常に重要です。
通常、羊水は
- 安全
- 保護
- 無条件の安心
を象徴します。
しかしボーにとっては違います。
最初に聞こえるのは、
母のヒステリックな声。
つまりボーは、
- 生まれた瞬間から
- 世界は安全ではなく
- 母は安心できる存在ではない
という刷り込みを受けています。
このため本作では、
- 風呂
- 水
- プール
- 水死体
といった「水」がすべて不安と死の象徴として機能します。
男性性と性トラウマ
屋根裏部屋に封印された巨大な男性器的クリーチャーは、
あまりにも露骨な象徴です。
これは、
- 性的衝動
- 男性性
- 父の不在
- 母に否定された自己
が混ざり合った存在です。
母はボーにとって、
- 女性
- 支配者
- 世界そのもの
であり、
ボーの中の「男性性」は行き場を失っています。
性行為の場面で起きる出来事も、
快楽と死が直結する歪んだ認知を示しています。
医者夫婦パートの再解釈
医者夫婦の家は、一見すると
- 保護
- 治療
- 安全
の象徴に見えます。
しかし実際には、
- 薬物依存
- 自傷
- 境界の崩壊
が蔓延しています。
これは
「治療を装った管理」
「保護を装った隔離」
の象徴と読むことができます。
ボーはどこへ行っても、
- 管理され
- 観察され
- 判断される
主体でいることを許されません。

最終盤の裁判|超自我的世界
ラストの裁判シーンは、
精神分析的に見ると超自我の暴走です。
- 母の声
- 社会の声
- 過去の罪悪感
それらが一体化し、
「お前は生きているだけで罪だ」
と断罪します。
ボーは一度も、
「自分の言葉」で反論できません。
これは、
自己が形成されなかった人間の最終地点です。
なぜこの映画は観ていて「疲れる」のか
それはこの映画が、
- 安心できる視点
- 客観的なカメラ
- 逃げ場
を一切与えないからです。
観客は終始、
ボーの不安の中に閉じ込められる。
これはホラー演出ではなく、
心理状態のシミュレーションです。
総合考察|愛着障害の成れの果てとしてのボー
ボーは「弱い人間」ではありません。
- 助けを求めている
- 正しく生きようとしている
- 誰も傷つけたくない
にもかかわらず、
安心できる他者を一度も得られなかった。
その結果、
- 世界は常に敵
- 自分は常に罪人
- 生きること自体が罰
という認知に囚われています。
『ボーはおそれている』は、
愛着が壊れたまま大人になった人間の、内的地獄を最後まで描き切った映画です。
鑑賞後にすること
- まずは最後まで観切った自分を労わる
- 「理解できなかった自分」を否定しない
- 他者の考察を読んで、世界が少し広がるのを楽しむ
この映画は、
理解するための映画ではありません。
感じ切るための映画です。
そしてその不安と恐怖の正体は、
決して他人事ではないところにあります。
それこそが、
この映画が本当に恐ろしい理由なのだと思います。

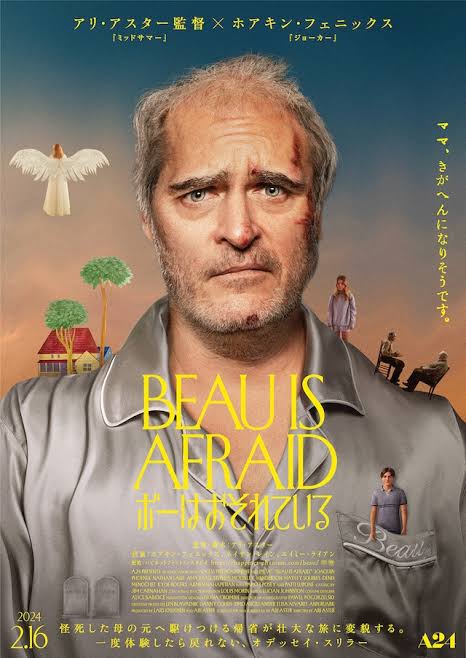


コメント